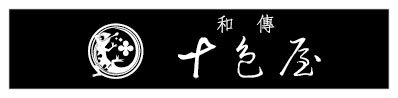先週の、2/19(金)。
~水都江戸の食卓と暮らしに学ぶ~ 江戸料理養生術を知るクラスの
第1回目が開催されました。
参加された方のアンケートからは、
「テーマが参加の決め手になった」という回答が多かったです。
ありがとうございます‼
この回答、とても、とても、とても、嬉しかったです。
講座では、
わたしとまりこ先生の方から以下の内容をお話させていただきました。
●水都江戸の成り立ち
●江戸の食文化の変化
●江戸の外食産業と食事情
●江戸の食から食養生を学ぶ
江戸時代前の江戸ってどんなところ?
「江戸」ということばの意味・由来、
「江戸」が初めて文書に登場するのはいつ?
というところから話を始めて、
「水都江戸」が都市設計のうえに出来上がっていったところのお話、
震災・第二次世界大戦(東京大空襲)・高度経済成長期により失われた
水辺の風景。
それを未来に残せるものとして、再度、水を主とした都市機構や
文化のミックスカルチャーの中心として未来に繋げていければという
お話いたしました。
まりこ先生からは、
2食→3食への食事の変遷、
魚河岸や野菜市場なども含めた江戸の食材と流通の発達、
外食産業について、
江戸時代には多くの料理本が出版され 一般市民の料理技術がどんどん発達
していったこと、世界が認めた「元禄時代以前の日本の食事」、
江戸の食事バランスのことなどをお話していただきました。
みなさま、大変熱心にメモを取りながら、
頷きながら、聞いてくだいました。
じぶん事として、
健康な心と身体を作るために必要な「食」、
そして「食養生」について、
ご参加者のみなさま、それぞれに、
得たものがあったのではないのでしょうか。
・・・続く!!
でんみらブログ(2016.2.26)